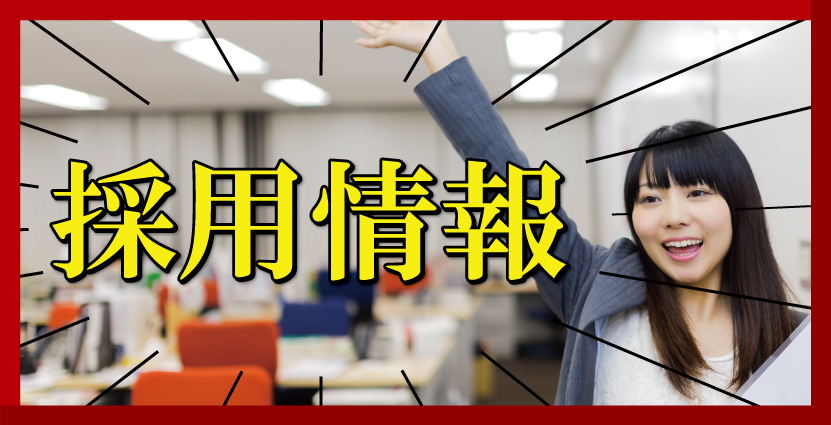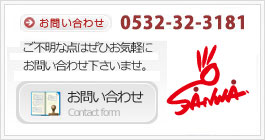Archive for the ‘三和新聞’ Category
第279号 継続はキッカケ!
| 第279号 継続はキッカケ! |
writer:渡 邉 啓 史
私は3年前より市の地域総合クラブに入会し、月2回ソフトバレーにて身体を動かしています。始めたキッカケは、校区の体育委員をやることになり、そこから気の合う仲間に誘ってもらいました。バレー未経験者ばかりなので和気あいあいと楽しく遊んでいます。また昨年からはソフトバレーからの繋がりで『インディアカ』にも誘われ、週1回参加しています。インディアカは私も経験した事がなく、皆さんもあまり馴染みのないスポーツではないでしょうか・・・?

分からない方の為に簡単に説明しますとソフトバレーの玉が大きなバトミントンの羽根に変わり、バレーのように手でレシーブをしてトスを上げ相手コートに打ち込むスポーツです。ちなみに両手で打つのは反則で左右どちらの手を使用しても問題ありません。始めて5カ月ぐらい経ちますが、アタックもトスも中々思い通りにならなくて、今はもっと上手くなれるように、練習するのが楽しみです。バレー経験が無い為、アタックの仕方やトスはどの辺りに上げたら良いのかなど、基本的な事をYouTubeで勉強しています!また更に4月からは『タスポニー』も週1回クラブにて開催されていますので、積極的に参加して行きたいと思っています。また聞き覚えのないスポーツか!と思いますが、こちらも簡単に説明すると手で打つテニスです。学生時代テニスをやっていたので、まだ入り込みやすいかと思っています。テニスはラケット(道具)を使っていましたがバレーやインディアカ、タスポニーは手で直接ボール・羽根を打ち返すのですが感覚が上手く掴めず、身体の一部なんだから道具を使うよりも上手くいくと思っていましが、不思議と道具を使うより上手くいかないのは、繊細な感覚なのでしょうか…ただの歳なんでしょうか…練習してもっと上手くなりたい次第です。
体育委員がキッカケで、たくさんの方と出会う事が出来た事と色んなスポーツをこの年から出来る事はちょっとしたキッカケを活かして自分の意志で行動している力だと思います。私は【継続は力なり】という言葉が好きで物事は続けて実行することに意義があり、それが自分自身の力になる!仕事も趣味もこの言葉を忘れずに物事に接しています。社会人になると学生時代の仲間と部活の延長線上でスポーツをやったりしますが、ある時期から仕事や家族に時間を費やす事でスポーツから離れていくタイミングが皆さんあると思います。私も社会人になりスキーやスノボーを子供が産まれるまではやっていましたが、マラソンを始めるまでは8年間まったくスポーツを行っていませんでした。マラソンもリレーマラソンから始め、今ではフルマラソンに参加し今年で11年続けています。ずっと練習してタイムが延び続けている訳ではありませんが足が故障して走れなくなるまでは、年2~3回の大会に出場する為に練習は続けていきたいと思っています。またソフトバレーやインディアカも今はとても楽しいのでこちらも継続して行こうと思っています。
ストレス社会の現状に何かストレス発散出来る事を見つける事が重要で、その趣味や目的の為にどう時間を【コントロール】出来るか、やる【目的】がないとどうしても重い腰が上がらないので、皆さんも何かちょっとしたキッカケでストレス発散出来る何かを見つけましょう!ちなみに私のストレス発散はお酒を飲む事で発散していると思っていましたが飲み過ぎるとあまり良い方向には行かなく、後で反省してしまうような事態も・・・そんな大変な事は滅多にありませんが(←少しでもあるんかい!?)今は身体を動かしスポーツに没頭する事で【気分転換】出来ていると思います。
会社でもI課長がソフトバレーを定期的にやる為に体育館を予約してくれて昨年の12月から楽しくやっていますので、一緒に楽しんで遊べるメンバー(社内・社外問いません!)を募集しています。継続していつかは大会にも参加出来れば楽しいかなと思っています。ちょっとしたキッカケから自分が行動する事により環境(仕事・趣味)が変わりますよ!思い立ったら即行動。過ぎた時間は戻らない。皆さんちょっとしたキッカケを大事に自分好みの環境に変えていきましょう!
第278号 魔改造
| 第278号 魔改造 |
writer:杉 浦 秀 幸
最近、楽しみにしているテレビ番組があります。それはNHK総合にて放送されている『魔改造の夜』という番組です。製造業に携わっている方であれば、ご存じの方もいるのではないでしょうか?2020年6月に放送が開始され、当初は不定期に放送されていましたが最近では1か月に1回程度放送されている番組です。内容は企業や大学生のエンジニアたちが玩具や日用家電などを主催者からのお題に合わせて改造を行い、その改造スペックを競うというものです。この番組が楽しみでたまらないのです!

1つのお題に対して3チームで競い合い、改造の予算は試作を含め5万円以内と定められています。お題が出されてから本番までの時間は1か月半しかなく、本番での試技は各チーム2回のみとなります。「悪魔の降臨です!」というセリフと共に1回目の試技が行われます。その前に出されたお題に対して試行錯誤を重ねて完成させる様子も見ることが出来ます。各チームがどのようにお題に対してアイデアを出していくか、最終目的は同じですが各チームが考えたものは形や機構などはまったく違うものになり各チームの戦略が見えてくるので毎回楽しみです。仕様・予算・納期がある中で完成させるという内容は私が携わっている仕事にも共通する項目になるので私も参加している気持ちで観ています。
1月末に放送された『おトイレ・ゆか・宙返り』のお題ではアヒルのおもちゃが便座に座っている状態で助走をして踏切地点に到達したら宙返りさせて目的地に正確に着地させる内容でした。どんなお題でも全てのチームが完璧を目指して製作をしているのですが、本番では上手くいかず失敗するチームもあります。この回も参加した1チームが1回目の試技でスタートボタンを押すと勢いよく前進して宙返りするはずでしたが、何故か後退してしまい失格となってしまいました。会場にいた方は何が起きたのかわからない様子でした。原因はモーターの配線間違いによるもので、前進と後退が逆に配線されていたようでした。2回目の試技の前に改修を行ったのですが結局修理が間に合わず『記録なし』という結果になってしまいました。1か月半かけて製作し、事前に何度も試運転したハズですがこのような単純なミスが本番で発生してしまいました。まさにこれが『悪魔の降臨』ということだと思いました。このような問題は私の職場にも潜んでいます。『今までも大丈夫』『前回と同じだから問題ない』など、このような考えでいると安心してしまい確認する作業を忘れて小さなミスが大きな問題に繋がることがあります。この安心してしまうということが【悪魔】という存在だと考えます。
さて、参加しているチームはライバルにもかかわらず他のチームのことを応援しています。失敗したときは自分たちが失敗したかのように落ち込んでいます。また、成功すると会場のみんなで大喜びして盛り上がっています。同じ目標に対して試行錯誤しながら共に挑戦してきた仲間であると感じているからこそ、このように共感し合えるものであり心温まる気持ちになる瞬間でもあります。
三和機工には【品質は我らの命です】という『朝礼唱和』があります。この朝礼唱和は全部で6項目あり、十数年前から社長の考案により各部署で毎日行う朝礼の最後に全員で唱和をして1日の始まりとしています。新入社員に於いては入社式の当日までに暗記して、式の最後に唱和をしてもらうなど社員であれば誰でも知っている行動指針となります。項目は『挨拶』『安全』『納期』『品質』『予算』『行動力』とあり、【品質は我らの命です】は文字通り『品質』の内容になります。最後の『行動力』は【思い立ったら即行動】【過ぎた時間は戻らない】と唱和は続きます。私は最近では何のために品質を守るのか自分自身に問いかけて【悪魔】の存在を忘れないように唱和をしています。私の職場でもお客様より依頼された設備をチームとして製作しています。品質は一人だけでは守ることは出来ません。チーム一丸となって品質の良い製品を作り上げてお客様に喜んでいただき、その積み重ねが信頼に繋がっていくと思います。さて今日もチーム全員でこころを【魔改造】をしていきましょう!
第277号 ラジオ体操
| 第277号 ラジオ体操 |
能登半島地震でお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りいたしますとともに、被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。思い起こせば1995年1月17日の阪神淡路大震災の発生した1週間前に三和機工に就職して早29年が経ってしまいました。30年で世の中のデジタル化は色々な分野で進歩しました。能登半島地震ではドローンやAIを搭載したロボット犬が投入されるなど人の手伝いをする分野では自動化が進んできました。しかし救助作業については人の力が重要である事に変わりはないと思います。異常気象による自然災害も毎年の様に頻発する様になりました。東南海や東海の地震も予想される中、新しい技術を使って救助活動の高速化が進んでいくかと思いますが、最後は助けたいという人の気持ちが高齢者の救助などの奇跡を起こすのでしょう。

さて元旦の大地震で世間の注目は能登半島の状況一色になりましたが、今年の『日本中の太田家』はニューイヤー駅伝の太田兄弟の活躍と箱根駅伝の青山学院大学の太田選手の快走によりテレビで何度も太田が連呼される事で【今年は太田イヤーになる!】と、『日本中の太田家』が良い初夢を見られたのではないでしょうか?そうなると次は「三和の太田はどうなんだ?」というお話になるかと思いますが、【安心してください。西尾マラソンでサブ4を達成しました♪】(サブ4とはフルマラソンを4時間以内に完走する事)…すみません!仕事じゃなくてプライベートなお話で。でも最近、伸び悩みで『サブ4』は諦め掛けていたので泣きそうなくらい嬉しかったです。そして、走る事を考える事は仕事にも通じる事があると気付きました。例えば省エネで走るとは体の動きをなるべく小さくして走る事だと思っていましたが、実際には全身の動きの連動により省エネで走れるという事が分かりました。全身を使う方が疲れると思うでしょうが、実際には腰回りの大きな筋肉で推進力を発生させて末端の筋肉は細かな調整をする感じで力を使いません。仕事においても誰かに丸投げしたままでは疲弊してしまいます。上長の采配と作業者の確かな技術が連動してこそより良い品質の製品が完成すると思います。自分の身体ですら思う通りに動かないのに他人同士で仕事を円滑に進めるには【目的に対する意識の共有】がいかに大切かという事を、身をもって気付かされました。皆さんも趣味の中から仕事に役立つ『気付き』があると思います。そんな気付きをどうやって仕事に変換するかを話し合っていけたら楽しいですね!
話を戻しましてマラソンの世界でもデジタル化が進みランニングウォッチの装着が当たり前になりました。1キロのラップタイムだけではなくコースの高低差・心拍数・足の回転数やピッチなど色々な項目が数値化されて表示されます。身体の疲れ具合も数値化され走る前に休息を促されたり、長い距離を走れば良く頑張りましたと褒めてもらえたりします。すっかり時計にデジタル管理されていますが、私の一番の体調のバロメータは会社で朝一に行う【ラジオ体操】です。世の中のメンテナンスフリー化に反比例して歳を追う事に原因不明の筋肉痛や関節痛に見舞われる事が多くなりました。そんな中、子供の頃から慣れ親しんだラジオ体操をしっかり行うと筋肉の張りや関節の強張りを教えてくれます。毎日行う事だからこそ体の変化に気づきやすいのです。イチロー選手の毎朝カレーライスと同じかもしれません。自分の軸をしっかり持って変化にいち早く気付きたいものですね。
そんな訳で全てデジタルに任せるのでは無く人間の感覚こそ信じるべき指標であると考えます。一生懸命物事に取り組むからこそ違和感に気付く事が出来、違和感に真摯に取り組む事で自分自身も仕事も品質アップに繋がって行くと思います。各個人の品質を上げる事が結果として会社の品質向上につながるはずです。現状に満足することなく切磋琢磨していきたいです。そして次は『サブ3.75』(フルマラソンを3時間45分以内に完走する事)を目指して頑張りまぁ~す!…すみません、結局仕事じゃなくてプライベートなお話しで…(苦笑)。
第276号 目標は大きく!
| 第276号 目標は大きく! |
writer:菅 沼 稔
明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い申し上げます。今頃は各々のお正月休みをゆっくり過ごされている事と思いますが、私はというと大晦日は家族ですき焼き、そして紅白歌合戦とお笑い番組のチャンネルを行ったり来たりしながら飲んだくれている事と思います。紅白が終わり『ゆく年くる年』が始まると近所の神社に家族で初詣に出かけるのがお決まりのパタ-ンとなっています。そして元日のお昼頃には地元の仲間と同じ神社に2回目の初詣(←もう初詣じゃないだろ!)からの新年会でまたまた飲んだくれる事となります。最近はお腹周りの脂肪も増えてきており尿酸値も上昇傾向ですので控えねばと思うのですが・・・

さて、昨年を振り返ると『ロシア・ウクライナ情勢』、『物価高騰』等、暗いニュースもありましたが、明るいニュースも沢山ありました。WBCでの侍ジャパンの活躍は本当にシビレました!侍ジャパンの完全密着ドキュメンタリ-映画『憧れを超えた侍たち 世界一への記録』では【WBC優勝】という大きな目標に向かって栗山監督を中心に代表選手の選考からメジャーリーグと日本プロ野球で活躍する一流選手達がそれぞれの役割を全うして、ひとつになっていく、試合だけでは分からない舞台裏の様子が描かれており初戦から決勝戦までの全7試合すべてにドラマがあり感動しました。そして、その後の日本代表の中心メンバーである『大谷翔平』選手のメジャ-での活躍は凄かったですね!毎日のようにスポーツニュースの話題を独占しシ-ズン終盤に怪我で戦線離脱したのにも拘わらずメジャ-リーグで日本人初となる【ホームラン王】を獲得しました。
大谷選手が高校時代に作った目標達成シートをご存じでしょうか。周囲9×9の合計81マスに細分化した目標を書き込んだもので彼はその中心に『8球団からのドラフト1位指名』という目標を掲げ、その目標を達成するために必要な要素を8つ記入します。更にこれらを達成するための具体的な目標をそれぞれ8つずつ記入して、細分化した目標を一つひとつクリアしていくと、最終的に成し遂げたい目標を達成できるというものです。これは【マンダラチャート】という有名な手法の様ですので興味のある方は調べてみてください。彼が設定した8つの要素の中には野球に関すること以外にも『人間性』や『運』が書かれており一流選手の器を感じます。今年は投手としては出来ないようですが、打者に専念した時にどんな活躍を魅せてくれるのか、とても楽しみです。
そしてもう一つ今年楽しみなのが21歳の若さで前人未到の【八冠独占】を成し遂げた将棋の『藤井聡太』棋士です。14歳でプロ入りしてから、そのまま無敗で公式戦最多連勝の新記録(29連勝)を樹立。藤井さんの活躍に刺激されたこの頃、我が家ではちょっとした将棋ブームとなり休日に息子と将棋を指すことがありました。我が家の次男坊が藤井さんと同い年で雰囲気が似ていたこともあり、家ではふざけて『よっ!藤井四段!』と呼んでいました。小学校の頃に将棋のル-ルを教えたのは私ですが久しぶりの真剣勝負は接戦で最初はかろうじて勝つことが出来ましたが、勝負を重ねるうちに負ける事もしばしば・・・。そして藤井さんが17歳11か月で初タイトルの【棋聖(きせい)】を獲得する頃には我が家の次男坊は高校の将棋部で部長を務めるようになり、負けると悔しいので今は勝負を避けています・・・。八つのタイトルの中で一番獲得が難しいのが『名人』と言われているのですが、彼は小学校4年生の時に「名人を超えたいです!」と語っていたようで、幼少期の目標を前人未到のスピ-ドで実現してしまうには才能だけではなく多くの努力が有った事と思います。私も彼らを見習って目標は大きく定め、その達成に向けて日々努力していきたいと思います。さぁ~皆さん!それぞれの【目標】に向かって今年一年!頑張っていきましょう!
第275号 人間、慣れだ♪
| 第275号 人間、慣れだ♪ |
writer:新 妻 吾 郎
最近、人に会うとよく言われる言葉がある。それは「…痩せたね!」と。次に出て来る言葉は「どっか体、悪いの?」次に「健康的なダイエット?」である。モチロン後者の方と答えると「何して?どうやって?」である。しかし、この『痩せたね!』の言葉こそ!もっと痩せよう!(維持しよう!)という私の活力になるのである。なので私は「もっと言って!」と、おねだりをする。その褒め言葉は私の中で『やる気』とマイナスイオンの様な『癒し』となって降り注ぐのである。

さて、気になっている方もいらっしゃると思うので~どうやって私が痩せたのかをお話しよう。あれは去年の夏頃であろうか?最近、体が重いな…と、ふと体重計に乗ったら~83kg…ヤーさんやんっ!と思いダイエットを決意した。しかし、その頃の私は腰椎ヘルニア手術&尾てい骨 骨折&坐骨神経痛のトリプルパンチで運動は出来ない。そこでAmazonさんをチラチラ見ていたら売上No.1の『トリプルバリア』なるモノが目に留まった。トリプルパンチの私がトリプルバリアに、しがみついた瞬間である!それは糖分・塩分・中性脂肪のトリプルを食べる前に飲んでバリアするという代物である。製造元NISSINさんの私は回し者ではないが結果が出ているので、何人の方々がポチッとな!と購入された事だろうか。我ながらソコソコの営業マンだ。買われた方々の結果は知らんけど…←無責任営業マン。
体重計に乗り、また痩せていると嬉しくなる。そして『もっとやれる事はないだろうか?』という【欲】が人間には出てくる。今年の夏からは寝る前に浅い(上げる高さが低い)腹筋を煩悩の数だけやっている。(つまり108回である。)更に!最近は1日8000歩以上~歩くことに目標を置き、出来得る限り実行している。そして現段階の状態は83kg→68kgで15kgのダイエットに成功中である♪一時は66kgまで行ったがチョイ戻り、平均すると68kgで約15ヶ月で1kgずつ落としていった計算になる。60kg台の体重なんて~30年ぶりぐらいだろうか?もう絶対に穿(は)けないだろうと思っていたデニムを捨てなくて良かった!この春に新調したスーツはブカブカになってしまい詰めてもらう事に…。でも差し引きすると『嬉しさ』が残る。しかし!先日の健康診断で私の身長からすると理想体重は65kgと明記されているのを見つけ…日々、精進するのみである。
話は少し変化するが~私は禁煙をして、もう19年経つ。吸い始めは15の時で←もう時効?21年間!吸い続けて36歳でやめた。やめる間際まで私は1日100本は吸うヘビスモで当時は1カートンが2日でなくなった。この話は2005年の三和新聞に『Oh My タバ子』と『Good-Bye タバ子』で載せているので、興味があれば読んで欲しい。さて!この話をすると、これまた同じ質問を受ける。それは「どうやってやめたの?」である。私は「吸わん事!」と即答する。「本当にやめたいのなら、どんなに気持ちが負けそうになっても〜吸わない事!」コレ以外には無いのである。
さて【人間、慣れだ♪】とお題目に掲げたが『慣れさせる』という事は『軌道に乗せる事』である。ダイエットや禁煙は一応~成功し、偉そうに能書きを並べ立てているが・・・軌道に乗せ切れていないモノも私には沢山ある。学習塾のCMだったか『やる気スイッチ』を探して、更に『それを続けていくスイッチ』を見つけない事には『慣れさせる事』にはならない。大袈裟に言えば【自分が決めたルール】を死守するイメージだ。良い癖づけをして慣れさせる事は非常に難しい。悪い?癖づけは、いつの間にかハマるものだが…。三和は変化して生きて来た。変化する事に慣れている会社だと私は自負する。さて、今年の締めくくりに!来年も~心と体と脳みそが喜ぶ【慣れだ】をしよう!
第274号 かんじんなこと
| 第274号 かんじんなこと |
writer:彦 坂 訓 克
母親が他界して親父1人と隣同士で住むようになってから数十年になりますが、我が家での夕食は一緒に食べるようにしており、夕食の支度が出来ると連絡して親父がトコトコやって来るというような具合です。最近の事ですが、家に来るなり「だいぶ、早い時間からこっちに向かって来る様になって来たな~」…共感を求める様に言い出してきた。なにが?全く何の事を言っているのかわからない。「何がどこから向かってくる?」って聞くと「向かいのサッシ屋の屋根の向こう方から四角の…、光って…」うまく説明できずにアレとかソレとかばかり。今も見えると言っているので何か飛んでいるのか思い、私と妻は外に出て夜空を見渡しました。それらしい物体は無く、何も見えなかったと伝えると親父は「あれが見えないのか?」って、納得していない様子ではありました。

親父に見える【物体】が何なのかが知りたくなり、次の日の夕食時に今も見えたのか聞いてみた。もちろん今も見えて「畳2畳分の大きさでそれが四方に光っていて4人くらいは乗れる。それが向こうの屋根の上の方からこっちに向かって来て、すぐ前の電線の所で消える!」って説明してくれたのですが…(←全く何かわかりませ~ん!?)帰り一緒に外に出て夜空を見上げ、親父は指を差しながら「あれが向こうの方からこっちに来る、前はもっと高い所から来ていたが最近は低い所を通ってくる。」と。指差す方向にはもちろん物体は無く、一点の輝いている星が見えるだけでした。姉にも確認して貰いましたが、親父の説明には全く違いは無く、見える物体にブレは有りませんでした。
親父は高齢ということは勿論ありますが、過去2度も『脳梗塞』が見つかり入退院を繰り返しています。その影響も有り2度目の脳梗塞から退院した直後は認知症が進み、酷い時にはテレビのリモコンと携帯電話の判別が出来ない。電気ポットのコンセントで携帯充電しようとしたり、車を家の前の道で駐車したり(←運転は即刻辞めさせました!)という有り様でした。しかし退院してから薬を飲んでいない事がわかり薬の飲用を続ける事で、今では時折何をしているのか解らない事とか、家族の名前がわからない程度の事は有りますが、日常生活で困るほどの認知症状は無くなっています。(割とシッカリしています)幻覚や幻視をいろいろ調べて見ると『人に関する幻視症状』(包丁を持った人が襲ってくる)や『動物に関する幻視症状』(ネズミが天井で走っている)とかが多いようで、決まった形の物体が見えるような症状は確認出来ませんでした。幻視には間違いないのですが、親父が毎日見える星が、畳2畳分の大きさでそれが四方に光っている様に見えている幻視には何か意味があるのでしょうか?
小説『星の王子さま』の一節にある言葉ですが【心で見なくちゃ、ものごとはよく見えないってことさ。かんじんなことは、目に見えないんだよ】と有ります。ただ目に映るものが必ずしも大切な事や真実とは言えないという事を言っているのだと思います。ものごとを正しくものを見ているつもりでも、自分にとって損とか得とかという自己中心的で自分勝手な見方で見たりして何が本当で何が偽りなのかを見極めることができ無くなってしまいます。どのような『思い』で見るかが大事なのでは無いでしょうか?目に見えるものばかりに心が左右されてしまい、大切なものを見失い、目に見えない多くのものに支えられていることに気付かなくなってしまっているのでは?と思います。
かの有名なアインシュタインの【自分自身の目で見、自分自身の心で感じる人は、とても少ない】という名言を恥ずかしながら最近知ったのですが、自分の目できちんと見ること。そして、自分の心で感じること。この2つを押さえないと、いいモノを作りだすことはできないという事の様です。現代はデータ社会で日々いろんなデータを目にしていますが、数値ばかりを追いかけて目にうつるものだけで判断するのではなく、どのような『思い』でそれらを見るかを大切にしていき、いいモノ作りが出来るようにしていかなければいけないのでは無いかと反省させられます。『心で見なくちゃ、ものごとはよく見えないってことさ。かんじんなことは、目に見えないんだよ』親父にとって心で感じて見えている【光る畳2畳】は、きっとかんじんな物なのでしょう・・。
第273号 私の履歴書
| 第273号 私の履歴書 |
writer:小 谷 野 一 彦
日経新聞の最終面に【私の履歴書】のコラムがあり、その人の半生が1ヶ月にわたって書かれていて、今回は少しそれを真似て・・・オマージュして書き進めたいと思います。
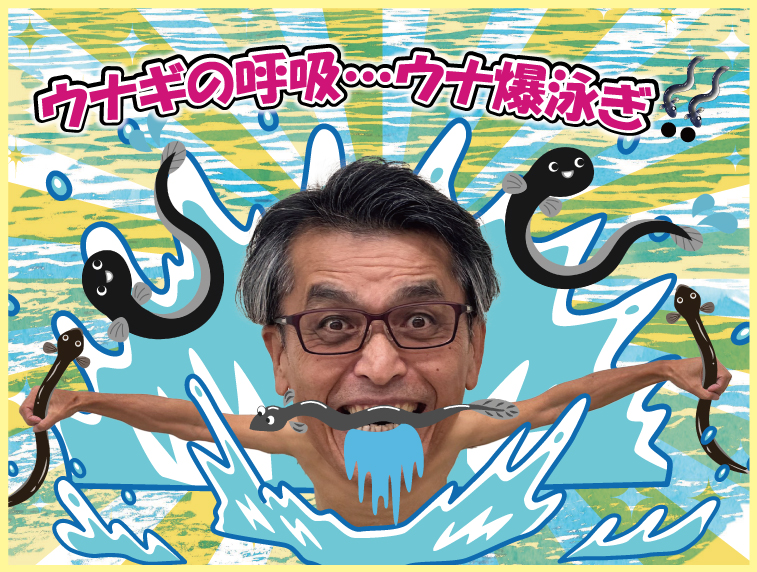
1964年12月30日!愛知県は、この豊橋の地で私は生まれた。3つ上の姉がいたが父は「なんとしても男の子が欲しい!」と、神社に足を運んだ際は男子を授かるべく願掛けは当然で、こちらを通ると男が産まれるという神話を信じ行動するほどに男子を希望していたようだ。そしてその願い通り私が産まれ、名前は【一彦】と名付けられた。【一】の意味はとにかく一番になれ!を望んでいたようである。私の気性としては今も負けん気が強く『人に勝ちたい』『人より前に出たい』という気持ちがあり、思い通りとはいかないが少しはその願いに応えられているのではないかと思う。【彦】は単純に自分と同じ一文字を付けたのだと思うが、ネットで【彦】を調べると『男性』を上品に呼ぶと『彦』となるようだ。残念ながら「品が無いなぁ~!」と言われた事が一度や二度ではないので、こちらは残念ながら望み通りとはいっていない・・・。
家庭環境としては、私が成人過ぎの頃まで父母共に『養鰻業-ようまんぎょう-』の仕事をし、住み込みの形であったため隣に親方家族が住んでいるという環境であった。父も母も常に親方に気を使って生活している事を、幼少の頃すでに感じていた。親方含め4家族が共に一軒長屋的な環境で暮らしていたため、今NHKで放送中の朝ドラ『らんまん』で庭に出て複数家族が一緒に食事するシーンは、とても懐かしく感じる。そんな我が家は玄関を開けると目の前にはウナギの住む養鰻の池が広がり記憶はないが2,3歳の頃から、その池でウナギと一緒に泳ぎ、そのおかげか小学2年生で25m泳ぐことが出来た。これは当時通った小学校の最年少記録で、その証としてもらった黒いラインを母が水泳帽に縫い付けてくれた。先生からも褒められて、とてもうれしかった記憶がかすかにある。そんな風にいつでも泳げる特殊環境であったため、夏休中はずっと長屋の仲間と一緒にウナギに嚙まれながら泳ぎ遊び、おかげで半端ないほど日焼けし夏休み明けの日焼け対決では負けたことが無い。そんな生活で学業はまったく駄目であったが、同じ暮らしをして一緒に遊んだ他の子は成績優秀だったため、どこでどういう勉強をしていたのか?いまだに解けないナゾである。
中学にあがり選んだ部活は当然『水泳部』その当時、室内プールなんてものは無く桜咲く頃の水泳練習は30分程度であったが全身が冷えて唇が紫色になっていた。暖かくなるにつれ練習量はどんどん増え、大会前には一日10kmを超えた。私が通った中学は市内で一番強かったが、それは練習量に比例していたと思う。『200m平泳ぎ』が私の種目で、1年は市内大会の新人戦優勝!2年3年とも市内大会優勝の3連覇を果たした。しかし東三河地区大会では惜しくも2位に甘んじ、父からは「だらしない!」の一言・・・予想もしていない叱責は、あまりにも悔しく父に憎しみを覚えるほどであった。県大会にも出場し5位と入賞はしたが全国大会には出場できず、水泳に打ち込んだ日々は中学3年の夏で終了した。そして受験勉強に専念と書きたいところだが『思春期特有の気になる事』で頭がいっぱいで・・・学力相応の高校に進学となった。
入学式で初登校して目に入った上級生は、もう帰りたい!と思うほど恐ろしく・・・不〇学生の吹き溜まり『ビーバップハイスクール』そのままであった。しかし、すぐに慣れて数か月で私自身もビーバップな学生に変身した。もめごとは日常茶飯事の学校であった。ある日、学校から母が呼び出された。もめごとの渦中の生徒・その親・先生、総勢10名ほどだっただろうか。原因は【私】という事は明白で・・・おさまりが付かないと判断した母は椅子から降りて床に土〇座をした、とっさに私もそれに倣ったが、訳が分からず涙が溢れた。今では笑い話にしているが、母にさせたその時の事は今でも申し訳ないと思っている・・・。今回はここまで。次回はその後の高校生活からと思っているが、人様にお話しできる内容とさせられるのかどうか・・・?
第272号 原点回帰
| 第272号 原点回帰 |
writer:松 井 千 昌
皆さんはじめまして。セミの鳴き声で朝起きてしまう夏が過ぎ去り、まだまだ暑い日は続いていますが体調はいかがでしょうか。身が細い私にとっては暑さも寒さも大の苦手なのですが、これ以上瘦せないように気を付ける努力が年中続きます・・・。

私が幼少の頃テレビで観たのは『仮面ライダー』『人造人間キカイダー』『秘密戦隊ゴレンジャー』『電人ザボーガー』など。全て知っている方はほぼ同じ年代だと思います。約半世紀前(←そんなに経ってしまったんか~い!)の特撮ヒーロー番組。塩ビのフィギアを持っていた方もきっと多いと思います。『仮面ライダー、戦隊シリーズ』は今も続いている人気番組であり、私の場合は初代となります。さて、このヒーローに共通している乗り物は【バイク】です。これらの番組の影響で将来はバイクに乗りたいと思った方は多いと思います。しかし私の場合はもう少し前に遡ります…。
父親は私が小学校に入学する頃まで車は無くバイクで通勤していました。記憶にはないのですが母親からの話しによれば父親は出勤する際、家の近くの急な坂道を押しがけでエンジンをかけ、一旦家まで戻って幼い私をシートに乗せて喜ばしてから出たそうです。こうした経験により、私の好きな【バイク】乗りになりたいと思ったのはここが【スタート】だったと思います。その後も将来乗りたいという思いは持ち続け高校生になると【乗りたい病】は増すばかり。しかしその頃は『三ない運動』(免許を取らない・買わない・乗らない)が非常に厳しく、学校にバレてしまったら停学処分プラス坊主となり親にも迷惑を掛けてしまうので我慢するしかありませんでした。ですが、乗るなと言われれば乗りたくなるもの。友人宅の広い敷地内(←本当です、多分…)で初めて乗った感動は今も覚えています。モトクロスバイクですがギアチェンジもすんなりと普通に乗れました。無事に高校を卒業し就職して、やっと乗れる♪との思いでバイク屋さんに何度も足を運んで、確か当時の定価約10万円のスクーターとヘルメットを買う事に決めました。あとは手続きや購入金の準備ができたら念願の運転が出来る!となった矢先に左手の親指を負傷してしまいました…。乗っている方なら分かると思いますが、方向指示器(ウィンカー)を出す時に使う指となります。包帯グルグルですし痛くて乗ることは出来そうもないので店に事情を説明し暫く置いてもらいました。ハンドルに掲げてあった【売約済み 松井様】の赤い札はそのままの状態でした。数ヶ月後ようやく痛みはあるもの乗り出しに辿り着いた時、やっと【スタート】ができ、その後も今までバイクは乗り継いでいます。今思い起こせば【将来の夢】を抱いてから長い年月が掛かっても思いは変わらず居られるのはいつか必ず叶う事だと思い続けていたからだと思います。
就職後『モノづくり』に関わることになり、フライス盤を使って加工作業を行うことになりました。最初に加工した物は、渡された治具と同じ物を製作するという指示でした。当時はデジタル数値ではなく、各軸のハンドルの目盛(今では老眼で見えやしない…)を読んで加工を行う方法でした。面引きしてザグリ加工していたら、エンドミルを折ってしまいました。当時刃物の知識も無く、コーティング(金色なので高いイメージ)された物だったので、初めての失敗に驚きましたが先輩の励ましの言葉を受けて次に進むことが出来ました。折れるとは思ってもいなかったので原因は切削条件や刃物摩耗だったのでしょう。この失敗から学んだ事がモノづくりの【スタート】だと思います。30年以上も前の事ですが、昨日の様に覚えています。
人には様々な【スタート】があり、省みることで初めの頃の自分自身の感情や心構えを思い出すことが出来ると思います。先生や先輩方の言葉や教えを忘れることはありません。物事が進化するのはとても早いのですが、色々と経験するのは必ず将来に繋がると思います。たくさんの失敗を経て、学び【初心】を忘れないと思います。私自身も失敗から多くの事を学びました。皆さんもそれぞれの【スタート】地点を思い出してはいかがでしょうか。
第271号 GAN&Princess
| 第271号 GAN&Princess |
writer:岩 本 祐 亮
8月…本格的な夏。いったい1日に何回「暑ッ!」と言わせれば気が済むんだぁ太陽は!と、文句を言いたくなる様な酷暑が続いています。私は寒い冬も苦手ですが夏は更に苦手な季節で早く秋が来ないかなぁと願いつつ…なんなら冬を飛び越えて春が訪れればいいのになぁとさえ思ってしまう程です。いっそ春と秋だけでいいじゃん?いやいやそれでは日本の美しい『四季』を感じる事が出来ないじゃないか!と一人ボケ突っ込みをしている間にもニュースでは毎日の様に熱中症の話題があがっています。私も、そう若くはないので体調管理には十分に注意していきたいと思います。皆さんも体調管理、熱中症対策を万全にしてこの夏を乗り越えましょう。

私事ですが今年の12月で、めでたく?40歳を迎えます。四十路?アラフォー?どっちでもいっか!(笑)…ってな事でまだギリギリ、ホントにギリ30代♪(←この発想が、もうおじさんまっしぐら!?)40歳というと日本人男性の平均寿命からすると丁度半分あたり。まさに人生の折り返し地点です。まだ半分なのか、もう半分なのかはこれから先の人生の歩み方次第かと思うと自分の【進むべき未来】【信じる道】に向かって突き進むのみです。40歳手前にして自分ではやはりいろいろな面で老けてきたなぁと感じます。見た目ばっかりは仕方がないので諦めていますが、特に年齢を感じるのは体の疲れです。30歳前後くらいまでは多少無理をしても寝て起きれば回復していたのにこの頃は全然ダメ…(哀)少し夜更かししたり遅くまで仕事をすると翌日だけではなく暫く疲れが取れないなんて事もしばしば。ここ数年で一気にキタなぁと感じます…。こんなネガティブな事ばかり言っていると元気な先輩方には怒られてしまいますね。気持ちだけは若くありたいものです。
私の妻はひと足先に四十路を迎えました。ご存じの方もいるかと思いますが豊橋駅の某店で21年間働いていたのですが、昨年退職し現在は絶賛『プー太郎』中。あっ、ちゃんと家事はしてくれています。本当に感謝しております。(←何故こんなにフォローに必死!?)今は新たな就職先を模索しながら『ノンビリ主婦』を楽しんでいるようです。そんな妻が退職後にどっぷりハマってしまったのが“king&prince”そう!あの有名ジャニーズグループの『キンプリ』です。今まではいわゆるアイドル的な物事には全く興味も無かったのですが何故か『キンプリどハマり』し、ハマってしまった最大の要因はカッコイイ&カワイイだそうです。そりゃ一般人のアラフォー男性じゃ相手になりません(悲)メンバーの中で誰か一人でも出演している番組があれば全て録画し、全チェックは当たり前。“YouTube”や“SNS”も隅々までチェックし、歌はもちろんの事!簡単な振り付けのダンスであれば踊れる程です。そんな『キンプリ』ですが先日5名のグループから3名脱退し2名で活動する事が発表され、既に新たなスタートを切りました。脱退したメンバー達は海外進出を目指したい!という彼らなりの【進むべき未来】【信じる道】に向かい、新たな事務所に所属するそうです。将来を約束されていたであろう若い彼らの選択と勇気には尊敬の念を抱きます。これからも夢に向かって突き進んでくれる事と期待しています。妻はメンバーが減ってしまった事に少し残念がっていましたが、残された2名含め彼ら全員の選択した道を全力で応援していくつもりだそうです。私も陰ながら応援していきたいです。
ところで人生の折り返し地点に差し掛かっている私の【進むべき未来】とは、、、
仕事ではもちろん、私生活においても長い人生の中では大なり小なりいろいろな問題や壁にぶつかります。その都度私達は自分の信念に従いあらゆる選択をしていかなければなりません。もちろんその選択が全て正しいとは限りません。テレサ・テンさんじゃないですが、『時の流れに身をまかせ』では面白くありません。私は自信と勇気を持って【進むべき未来】へ向かい自分自身の選択を尊重して生きていきたいと思う今日この頃です。
さて、あなたにとっての【進むべき未来】とは、、、、、
第270号 PARENT AND CHILD
| 第270号 PARENT AND CHILD |
writer:新 妻 吾 郎
今月の7月11日(セブンイレブン)で、私は55歳になる。来年は吾郎〜56歳なので55→56で、ゴーゴーゴロー♪となる。←だから、なんだ?しょーもなっ!…ご存知の方も多かれと思うが私は今この歳で19歳・7才・4ちゃい・1ちゃいの子供がいる。19歳の勇吾(ゆうご)は色々あって割愛するが離れ離れで暮らしている。お互い忙しいので会うのは年に2回程度か。その時は下の3兄妹にも会わせて皆、最高に『癒しの時間』を過ごしている。勇吾は今、母親には反抗期。しかし親父の私には全く反抗をしない。まぁ〜確かに年に2回しか会えない時に、下の3兄妹もいて反抗して小遣いも貰えないなんてアホやから反抗はせんのであろう。まぁ〜反抗され武力行使で来られた場合、愛息は剣道を小学校からやっていて全国でも成績を残し握力は90kgを超える。なかなか厳しい戦いになるだろう。我が身を振り返れば腰椎ヘルニア・尾てい骨 骨折・坐骨神経痛のトリプルパンチに高血圧・糖尿病・高コレステロールと成人病まっしぐら!…でも、寝かせてサブミッション(関節技)なら勝機あるカモ?と、いつの世も親は息子に負けたくなく子は親に勝ちたいという世の常である…。

1ちゃいの莉來(りら)と4ちゃいの将吾(しゅうご)は目下!めっちゃ『イヤイヤ期』の真っ只中!莉來は私の誕生日の次の日に生まれたので今月2ちゃいだ。55歳の「ゴーゴーゴロー♪」なんて言っても2ちゃいの祝いにゃぁ〜敵わない。私の誕生日イベントなど莉來の…金魚のフンにも満たない扱いだが、まぁ〜嬉しい限りだ。ただ『ゴロー56歳イベント』の来年はシッカリガッツリやらして貰おうと企てている大人気ない男親だ。4ちゃいの将吾は『しょうご』と読まず『しゅうご』と読む。漢字は『将』の漢字を使いたく、通常は『しょうご』と読むが調べていくと『しゅうご』とも読む文献を見つけ…要は『しゅうご』の中に『ゆうご』が入っていて、お前たちは兄弟なんだよ!と云いたかっただけである。なので字画が良いか悪いかなどは調べた事もない。
シューゴはヤンチャでリラはおてんば娘にスクスク育ってくれているが、まだ人間というよりも欲望のままに動く動物に近い。特に『疲れた』『眠い』『腹減った』は、それなりの言葉とジェスチャーで伝えてくるも要求が通らない時は途轍もなくデカい声での『ギャン泣き』が止まらない。特にリラの声は半端なくデカく、よく通る声で…家でも外でもドコでも大の字に寝そべってギャン泣きし、泣き止むまで1時間は止まらない。スマホで『アンパンマン』の動画を見せると稀にだが泣き止むので、その時はアンパンマン様様だ。このドコでも大の字ギャン泣きの光景は幼き頃の妹を彷彿させるので…DNAだなぁ〜と思う。大体、男はボケェ〜と!女の子はおマセなので2ちゃい差はあるが同い年だとお互い思い込んでいるようで2人でケンカになる時はマジでグーパンチの連打である。大抵はリラがクリーンヒットを決めてシューがマット?に沈み、またギャン泣き…我が家はいつでも『カオス状態』である。
長女7才の『ひまり』は小2だが最近やたらと色気づいてきた。ネイルチップとかいう簡単に取り外しができる『つけ爪』をし、下手な化粧をして外へ出たがるのだ。莉來にもネイルチップを付けてやって、その横で将吾も見よう見真似で付けている。←お前はやめとけよ。4年ほど前はローラー滑り台で顔面から転げ落ち!救急車で運ばれかけ…顔面アザと血だらけで初登園し、今でも毎日どこかをケガしては血を流して帰って来る…血は争えん?これまたDNAか…。
さて、人を育てるという事は非常に大変なことであり『仕事』でもある。今回は我が子を中心に書き綴ったが『人材』を『人財』と育て上げていく事もまた至難の業である。お題目の『親子(翻訳)』ではないにせよオーバーラップして捉えて頂きたいと、斯様(かよう)に思う次第である。子育ては親育て。出来の悪い子ほど可愛いと云うが…子供に教わる事もある。子供が持って来る『世界』がある。子供と共に成長する。子供は『最高の癒し』と『最大のストレス』を引っさげてやって来る。だが頭を支えて髪を洗う時の頭の重みを、ずっと手が憶えている。命を投げ出しても守り抜く存在である。新妻の妻は『育児』に毎日~24時間!翻弄されている。感謝して止まない。手伝える時は手伝うが…あまり家にも居ないので、頭は下がりっぱなしの思いである。
« Older Entries